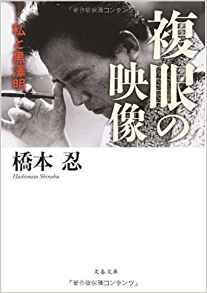『複眼の映像 私と黒澤明』(橋本忍著/文春文庫)
著者の橋本忍氏は、黒澤明と共に代表作の『羅生門』(1950)、『生きる』(1952)、『七人の侍』(1954)の脚本を書いた脚本家だ。
1918年生まれ。黒澤明の8歳年下だ。
当時、黒澤明は映画監督であったが、同時に映画の脚本も書いていた。
『姿三四郎』を撮った最初期(1943)には単独で脚本を書いて撮影していたが、5作目『わが青春に悔なし』(1946)以降は、他の脚本家を誘って共同で脚本を書くようになった。
当事者である橋本忍がいうには、共同脚本のメリットは「三人寄れば文殊の知恵」のとおりらしい。
人間1人のアイデアには限界があるが、2人、3人が集まって能力の限界まで知恵を出し合えば(「複眼」で作品を見つめると)、その集積によって1人では実現できない完成度の高い豊かな作品が生まれるのだという。
デメリットは時間や予算や手間が何倍もかかること。
― ― ―
黒澤明監督は、1951年のヴェネチア映画祭で『羅生門』によって金獅子賞(グランプリ)を受賞した。
戦後まもない時期で、受賞した当事者たちはヴェネチア映画祭など知らなかった。
日本人初の快挙だという。
それ以後現在にいたるまで、黒澤明は映画の神様としてあがめられている。
が、実際の黒澤明のひととなり、言動、仕事の進めかたというのは私たちにはわからない。
それを、そばで見聞きしていた著者の橋本忍が細かく教えてくれるのだ。
『複眼の映像』には、『羅生門』『生きる』『七人の侍』の創作現場の様子がこれ以上ないほど生き生きと描かれている。
黒澤明は40〜44歳、橋本忍が32〜36歳。いちばん気力が充実し、情熱が燃え上がっていた頃の創作現場の話だから面白いのなんのって。
脚本家の黒澤明と橋本忍(と小國英雄)が、箱根や熱海の宿に文字どおり自ら缶詰になって、毎日朝10時から午後5時まで7時間規則正しく執筆をおこなう。
1日平均半ペラ(200字詰め原稿用紙)で15枚を書く。20日間で映画1本分の300枚が仕上がる目安だというが、実際には1稿、2稿、決定稿と念入りに書きなおすのでもっと時間がかかる。
映画1本分の脚本を書く労力については、マラソンで42.195キロを走り切ることに例えられている。
それにしても、黒澤明が能好きで食事のときに世阿弥の話をするだとか、『七人の侍』をドボルザークの「ニューワールド(新世界より)」風に作ろうと橋本忍に提案しただとか、当時のリアルな現場で交わされる会話がカッコいい。
橋本忍がイチから脚本家修行をはじめる経緯や、良い脚本に欠かせない要素など、実技についても懇切丁寧に記述されている。
― ― ―
この本には『複眼の映像 私と黒澤明』というように、橋本忍と黒澤明の運命的な出会いから別れまでが詳細に綴られている。
別々に仕事をするようになってからも、腐れ縁というか、橋本忍は黒澤明と無縁とはなり得ず、その後も最後まで彼の仕事ぶりを見守ることになる。
結果的に黒澤明の作品のピークは、橋本忍と共同脚本した『羅生門』『生きる』『七人の侍』の頃だったようだ。
黒澤明は決して映画の神様ではなく、創作者として1作1作生みの苦しみを経験し、大成功と大失敗を何度も経験し、最後まであがきながら生きてきた人間だったということがわかる。
この本を読んで意外だったのは、映画の脚本家は映画の設計者であり職人であるという記述だった。
橋本忍は、黒澤作品の失敗は、脚本家としての黒澤明が職人であることをやめて、芸術家になったことが一因であると分析している。
私は映画というのは芸術作品で、映画人は芸術家だと思っていたが、冷静に考えると映画づくりには技術者が多くかかわっている。
脚本家も技術者の1人で、小説家とは別種の作家であるという。
橋本忍によると、小説を書くよりも、脚本を書くほうが数段むずかしいそうだ。
著者は一流の脚本家なので、文章を読んでいるだけで、まるで映画を見ているように当時の情景が生き生きと立ちのぼってくる。
映画を1本見終わったときのような興奮と満足感を得ることができる。
脚本家志望の人、映画にかかわる人、映画ファン、創作活動に興味がある人、ただの読者好きにもぜひ読んでほしい1冊です。