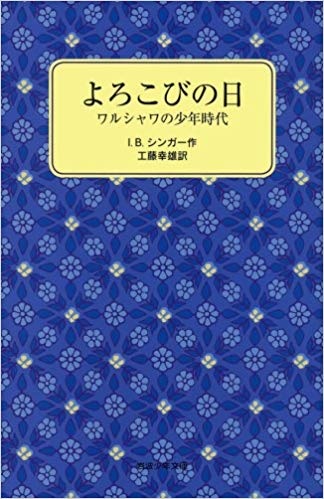英国におけるユダヤ人差別
オーウェルは大変率直な人だ。
「英国におけるユダヤ人差別」などという誰もが避けて通りたいテーマでも自分が見聞きしたユダヤ人差別の実例をあげて、この問題について屈託なく論じようとする。
「英国におけるユダヤ人差別」は20ページ程度の短い評論だが大変読みごたえがある。
英国人は理性的で客観的に物事を見るイメージがあるが、いくら知的水準が高い人でも、ノイローゼ的な差別意識から自由にはなれないみたいだ。
知識人は自分がユダヤ人を差別することを恥じていて、「ユダヤ人差別」と「ユダヤ人嫌い」を区別しようとする。
そこには矛盾があるとオーウェルは指摘する。
ユダヤ人差別について検討しようとするなら、「なぜ世間の人たちはユダヤ人差別を・・・」と始めるのではなく、「なぜ私はユダヤ人への差別思想にとらわれるのか?」と、自分の心の底をまずチェックすべきだとオーウェルは言う。
正論だが、そういうことを冷静に考えたり、あえて指摘する人は少ない。
私たち日本人にとってユダヤ人は遠い存在で差別意識を持ちようがないが、「英国におけるユダヤ人差別」の文章を「日本における韓国人差別」や「日本における中国人差別」に置き換えて読むと、その差別意識が驚くほど似ていることに気づく。
一方、信仰深いユダヤ人には特殊な思想がある。
自分たちは神に選ばれた民であるという選民思想だ。
有名な割礼は神との契約のしるしだという(今まで具体的にどうやるか分からなかったが、今回画像検索したら想像していたよりも切る範囲が広くて驚いた。痛そう!)。
「自分たちは神に選ばれた」「ユダヤ人以外は人でなし」「(異教徒に対して)偶像崇拝者」などと考えて、ユダヤ人同士で会話する。
ユダヤ人差別ではなくユダヤ人の方が異教徒を差別してる気もする。
ユダヤ人の結婚相手はユダヤ人に限る。
昔は日本人の親も自分の子供が外国人と結婚することを嫌がった。「純血主義」というのだろうか・・・。生理的な嫌悪感というか、日本人の場合は直接宗教に基づいていないと思うけど。
やっぱりオーウェルの言うとおり、(生理的な)嫌悪感=差別意識であり、たとえば「ユダヤ人は嫌いだけど差別意識はない」というのは矛盾で言葉としておかしいのだろうか?
でも日本人同士でも生理的に嫌いな人間がいる。=差別意識なのだろうか?
というか、個人個人に対してはユダヤ人でも、日本人でも、韓国人でも、中国人でも「嫌い」という人はいるけれども、それをユダヤ人全体、日本人全体、韓国人全体、中国人全体に広げると、民族差別になるということか。
でも私は日本人なので、ある日本人が嫌いでも、日本人全体を嫌悪することはできない。自分もその中に含まれているからだ。
オーウェルもユダヤ人がユダヤ人を差別することはないと言っている。確かにそうだ。
ひとりに対する印象を全体に当てはめて嫌っては(差別しては)いけないということか。
でもたとえば私が住む町にユダヤ人のコミュニティができたとする(移民?)。
見た目も言葉も食べ物も宗教儀礼も生活習慣も違う人たちだ。
日本人とは違う顔つき、帽子、服装に違和感を抱く。異質な物には自然に警戒心が働く。
違和感とか警戒心が生理的な嫌悪感に結びつくことはあるだろうか?
もしあれば、この場合はひとりから全体への嫌悪感ではなくて、一気にコミュニティ全体が対象になる可能性がある。
でも実際に世界中のいろいろな国の作家が書いた本を日本語で読めば、同じ人間の感覚がそこにあることがわかる。
たとえば、この記事の下の方で紹介するポーランドのユダヤ人・シンガーの『よろこびの日』はワルシャワのユダヤ人コミュニティの様子を自伝的に描いたもので、服装、宗教、言語、習慣が異なるものの、基本的な考え方、行動、喜怒哀楽の点では、日本人もユダヤ人も変わりないと分かる。
ただ見た目は分かりやすいが、他人の頭の中はなかなかうかがい知れないので、同じ人間同士でも理解し合うのはとても難しい(たとえ日本人同士でも)。
逆にワルシャワの街に移民した日本人のコミュニティができたとする。顔つきも、言葉も、生活習慣も違う群れるアジア人をポーランド人やユダヤ人はどう思うだろう?
たとえどう思われようとも日本人である私はワルシャワのコミュニティで家族と慣れない環境での日常生活をおくり続けるし、嫌われる理由、差別される理由を思いつかない。
きっとおしゃべりしてちょっとでも知り合えば、ポーランド人も、ユダヤ人も、私のことを少しは好きになってくれるかも。
他民族に対する差別意識はなかなか無くならないものかもしれないが、「差別意識は一種のノイローゼ」というオーウェルの言葉を心につぶやいてみれば、一瞬冷静な気持ちになれるかもしれない。
さらにオーウェルは、ノイローゼの背後には「ナショナリズム」というもっと大きな病気がひそんでいるのだという。
この病気は難敵そうだ。
『オーウェル評論集』のAmazon商品ページ(Kindle版)
ユダヤ人の日常生活が描かれた本
『よろこびの日―ワルシャワの少年時代』
アイザック・バシェビス・シンガー著
(岩波少年文庫)
リアルなユダヤ人、ユダヤ人の日常生活について知りたければ、ノーベル文学賞作家アイザック・バシェビス・シンガーが書いた『よろこびの日―ワルシャワの少年時代』がおすすめだ。
シンガーの父親は、ユダヤ教(ハシド派=正統派)のラビ(坊さん/指導者/研究者)だった。
シンガーの母親の父もユダヤ教のラビだった。
だからシンガーは生粋のユダヤ教徒の家に生まれたことになる。
ユダヤ教徒は日常生活ではイディッシ語を使う。イディッシ語はドイツ語系でヘブライ語とも共通点がある。
※ヘブライ語=パレスチナのヘブライ人が使っていた言葉。ユダヤ教の聖典・旧約聖書はヘブライ語で書かれている。
シンガーは幼い頃から親しんだユダヤ人の日用語であるイディッシ語で文学を書いた。
シンガーは1904年にポーランドのラジミンという町で生まれた。
シンガーが3歳の時に一家はワルシャワに引っ越した。
父親の職業はラビで、宗教行事をおこなったり、人々の相談にのったり、裁判官の役割もした。
ラビの給料は寄付にたよっていた。
集金係に金額をごまかされたりして、シンガー家は非常に貧しかった。
両親、姉、兄、シンガー、弟の住むアパートはスラムのような建物で、部屋にはガスもトイレもなかった。
中庭の小屋にあるトイレは、トイレを我慢したくなるくらい汚かった。
ユダヤ教の教えを実生活でも真面目に守ろうとするハシド派のユダヤ人は、ユダヤの古い風習に従った身なりをしているのでひと目でそれとわかった。
男性はあごひげを生やし、もみあげには長い巻き毛をたらす。
女性は他人に地毛を見せないためにカツラをかぶる。
ハシド派では、女性を名前で呼ぶことは許されない。
シンガーの父親も、母親に用事があるときは「ねえ、ちょっと」と声をかけ、決して名前を呼ばなかった。
シンガーは4歳からヘーデルという男子用の宗教学校に通い始めた。
そこではイディッシ語、『モーシェ五書』といったユダヤ人の生活に不可欠の知識を教えられた。
※『モーシェ五書』=旧約聖書のはじめの5巻を指す。ユダヤ民族の歴史、神との契約について書かれている。
つまりシンガー一家の生活はユダヤ教一色の家庭だった。
そんな生活がつまらないかといえば、ぜんぜんそんなことはない。
シンガー少年は生まれながらの作家気質で、感受性が強く、好奇心旺盛、知識欲のかたまり、お話を作り語るのが好きだった。自他ともに認める変わり者。
父親が信仰心を植えつけるべく語って聞かせたユダヤ教徒に伝わる奇跡の話、幽霊、悪魔、小鬼はシンガー少年の想像力に拍車をかけた。
シンガー一家のまわりには、悪いユダヤ人も、良いユダヤ人も両方いた。
ユダヤ人コミュニティの自然な姿が物語の中で描かれている。
シンガーの父親は時間があれば『タルムード』の研究に没頭しているような学者気質だった。
※『タルムード』=『モーシェ五書』を読み解くための基本事典
ハシド派にとって物欲は敵だ。
「物質的な世界の楽しみによりかかるな、いずれしっぺ返しがくる、ただひたすら神に仕えよ、聖書を学べ、ほかのいっさいは滅びる」
(『しつけの鞭』という書物にある教え)
こんな宗教的な環境で育ったにもかかわらず、シンガーはまわりのあらゆる物を観察して、大人の話をこっそり聞きとり、自由にのびのびと発想する人間に育った。
父親はユダヤ教の頑固で厳格なラビそのものだったが、母親は根っからの合理的思想の持ち主、11歳としの離れた兄は古くさいユダヤの風習にかなり批判的で、当然父親ともケンカが絶えなかった。
兄は結局アメリカに渡ってしまったし、その後シンガーもアメリカに渡り、市民権を得て、そこで文筆家として一生を終えた。