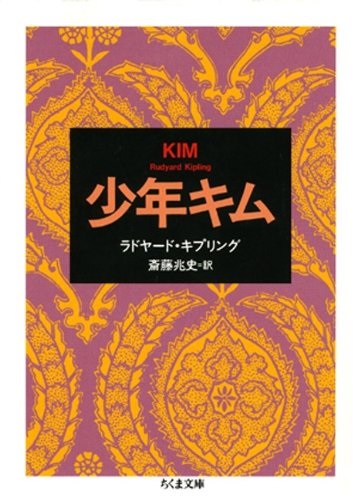キプリングとインド
大英帝国時代(インド統治期間は1858-1947)、植民地のインドなどに赴任し、その地で子供を産み、育てるイギリス人は多かった。『少年キム』の作者であるラドヤード・キプリングは、インドで生まれたイギリス人の一人である。
キプリングは5歳までインドで過ごし、その後イギリスで教育を受けて、16歳のときにインドに戻って新聞記者になった。24歳のときに再度イギリスに渡る。
幼少期から若い時代に体験したインドが、キプリングの作品の源泉になっている。
『少年キム』のあらすじ
(※ネタバレありです)
キムはイギリス人で白人だが、インドで貧しい孤児として暮らしている。現地人同様に黒く日焼けして、ウルドゥー語をぺらぺらと話す箸にも棒にもかからない悪童だ。
アイルランド人の母親は「大佐の家の子守女」で父親は「アイルランドのマヴェリック連隊の若い軍旗護衛軍曹キンバル・オハラ」であった。キムが3歳のときに両親はすでに亡くなっていた。
ある日キムはチベット人のラマ僧と知り合った。
年老いたラマは「矢の聖河」をさがしている。釈尊が放った矢の落ちた場所から泉が湧いて大河となったという伝説にあやかりたいと切に願って旅をしている。
これまで聞いたこともない不思議な話ばかりするラマは、珍しい宝物のように、キムの目には映った。キムはその宝物が欲しくなった。
キムは自分からラマの弟子を買って出て、ベナレスまでお供することになった。
実はキム自身も、亡くなった父親が予言した「緑野の赤牛」をさがしていた。
物語の終わりまで「矢の聖河」をさがす旅はつづく。
舞台は北インドが中心になっている。
ラホールからアンバラ、デリーを経てベナレスにいたる大幹道を2人は移動する。
実は、キムの「緑野の赤牛」は比較的はやい段階で発見される。
そのためキムはサーブ(在印イギリス人)の学校で英語の読み書きなどに始まる教育をうけるはめになる。
休暇中は一癖も二癖もある大人たちにあずけられ、スパイの勉強をさせられる。
羅針盤・水準儀・側鎖をつかって測量の技術と理論もまなぶ。測量の道具がなくても距離をはかれる方法もまなぶ。
そして、インド・イギリス・ロシアのスパイ同士がくりひろげるグレート・ゲーム(闇戦争)にキム自身も好んで巻き込まれていくことになる。
インドを舞台にくりひろげられる唯一無二の冒険譚。
多種多彩な登場人物
在印イギリス人のキムやチベット人のラマ以外にも多種多彩な登場人物がでてくるのがこの本の魅力だ。
・マハブブ・アリ:大金持ちのアフガン人馬商人。ラホールでのキムの取引相手。キムの情報収集能力を高く評価している。
・アーサー・ベネット:英国国教会の従軍牧師。マヴェリック連隊に所属している。
・ヴィクター神父:アイルランド分遣隊のローマ・カトリック司祭。
・クライトン大佐:イギリス人。インドの最高司令官。ウルドゥー語を流暢にはなす。キムの出自が判明した後はキムの管理者となる。
・ラーガン:シムラの有名人。インド人を相手におもちゃや宝石、古道具などを商っている。金貸しもする。あだ名は「玉磨きの先生」。
・ハリー・チュンデル・ムーケルジー:おしゃべりなベンガル人。カルカッタ大学文学修士。医学・薬学にも通じている。変装の名人。あだ名は「バーブー(インド紳士)」。
『少年キム』の感想
まるでキム自身であるかのように、キプリングはインドで暮らすイギリス少年を活写している。
イギリス人がこれほどまでにインドの土地・人びと・言語・風俗に精通しているというのは驚きだ。
私は最近イギリス人が書いた小説を通じてインドに触れている。イギリス人は日本人よりもだいぶインドになじんでいて、とても詳しい。
同じくイギリス人であるE.M.フォースターの『インドへの道』もあわせて読んでほしい。
イギリス人の一部の人はインドとインド人を愛しているのだと理解できる。
関連記事:インドへの道/E.M.フォースター