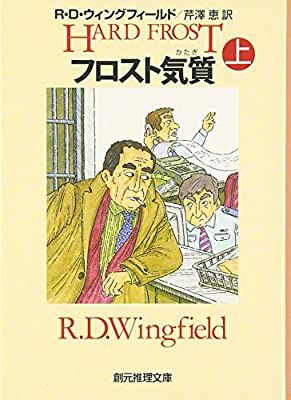R・D・ウィングフィールドによるイギリスのミステリー「フロスト警部シリーズ」の第4弾を読んだ。
(※以下ネタバレありです)
『フロスト気質』の特徴
1. 話が長い
ミステリーでは必ず事件が起こる。
たとえば殺人事件。
主人公の刑事が事件の謎を解き、犯人を追い、逮捕してストーリーが完結する。
場合によっては1つの小説の中で2件以上の事件が起こることもある。
表面的には無関係に見える2つの事件は、実は深いかかわりがあったというパターンなど。
ところが『フロスト気質』は2-3件の事件どころじゃない。上下2巻の小説の中で数えきれないほど事件が起こる(記事末尾にリストアップ)。
デントン市警の管轄区域内でこの時期、集中的に多くの事件が起こるのだ。
『フロスト気質』のメインとなる事件は7歳の男の子の誘拐事件だった。
少年の命がかかっていて発見するまでは時間とのたたかいなので、主人公のフロスト警部と部下たちは文字どおり4日間にわたって不眠不休の捜索を余儀なくされる。
誘拐事件だけでも手いっぱいなのに、これでもかというほど事件が頻発するのだ。
まるでイギリス版の『ミッション:インポッシブル』だ。
2. 主人公がダメ人間
フロスト警部は小説の主人公としては珍しいくらいダメ人間として描かれている。
実際に事件の捜査中、何度もミスを重ねる。
チームワークに欠かせないいわゆる「報連相」はどんどん怠る。
いつも間の悪いタイミングで下品なジョーク/小話を披露する。
身だしなみにまったく構わず、浮浪者同然のたたずまいをしている。
記憶力がほとんどない。
自分の直感力を信じているがハズレばかり。
煙草を吸いすぎ。
違法行為が多すぎ。
でもいつの間にかこのキャラにはまってしまう。
3. 臭いものの登場回数が多い
捜査の一環でドブさらいをするシーンでは、何年も前の腐ったゴミ袋を引き上げたり、動物の腐乱死体を見つけたり。
清潔志向・潔癖症の日本人からすれば「信じられないくらい汚いなあ」と思う状況が多いし、ウィングフィールドは情け容赦なく汚穢シーンを描写するのが好きだ。
イギリス流のブラックユーモアの発露かもしれない。
4. 登場人物のクセが強い
イギリスの小説などを読んでいると、日本人に比べて登場人物の個性が強いことに驚かされることが多い。
主人公や脇役たちが個性的というより、一人ひとり全員変わっているという印象。
日本みたいな同化圧力がなければ、人間というのはこんなにてんでんばらばらに仕上がるものかという実験例を見ているかのようだ。
フロスト警部シリーズだけでなく、イギリスの小説には驚くべき個性の持ち主が山ほど登場する。
個性というのは日常的にぶつかり合うものだ。
でも各人の性格の違いは当然として、目的にむかってチームワークも発揮できるというのが興味深い。
多様性はしばしば不快なものだが、違いを越えた先に面白い化学反応が生まれることもある。
未来の日本もこんなふうになるのかなあと考えたりする。
イギリスはアメリカと同じ英語圏だが、国のキャラクターは正反対といっていいほど異なる。
日本では生まれたときからアメリカ文化の洗礼を受け、その影響から一生のがれられない。
新境地を見つけたい人にフロスト警部シリーズはおすすめだ。
『フロスト気質』で起こった事件
(※ネタバレ注意)
・7歳の少年が行方不明
・8歳の少年の死体を発見
・15歳の少女の誘拐事件
・水道作業員を装った連続窃盗事件
・幼児の連続刺傷事件
・石炭貯蔵庫で腐乱死体を発見
・民家で3歳/2歳/生後11ヶ月の子どもの死体を発見
・上記の子どもの母親は行方不明
・デントン市内で偽造紙幣が流通
・秘密の写真をネタにしたゆすり事件
・タンクローリーとポルシェの衝突事故