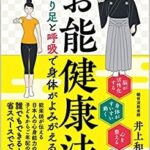私の盲端/朝比奈 秋
投稿日:2024年10月22日 更新日:
(※ネタバレありです)
私の盲端
朝比奈秋著『私の盲端』を読んだ。
書評を読んで興味をひかれたからだ。
『私の盲端』は、今まで読んだことのない内容だった。
著者は医者だというが、確かに体とか内臓とか、一般の人が覗けない、描写できない部分について念入りに書かれている。
人工肛門をつけたばかりの女子大生・涼子が主人公だ。
私にも十数年前から人工肛門生活を送っている会社員の友だちがいるので、とても興味があるテーマだ。
私は好奇心が強いので、『もっと人工肛門について詳しく聞きたい』と思っているが、友だちは詳しく話したくないかもしれないので、普段はそのことにはまったく触れない。
だからその反動で、人工肛門について書かれた本や漫画は貪るように読んでしまう。
『私の盲端』は、人工肛門について私が知りたいような事柄について微に入り細に入り語ってくれるのでうれしかった。
読者は皆驚くと思うが、人工肛門の非常に不思議な使い方まで複数載っていた。
『医者(作者)にとっては、内臓も機械の部品的な見え方・扱い方になるのだな』と感じて、医者の目を通して体や内臓を見ると、これまでとは違った世界が広がるようだった。
朝比奈秋は京都生まれだという。
『私の盲端』も関西の方が舞台だからなのか、著者が医者だからからなのか、登場人物たちの体と体の距離がとても近いことが気になった。
家族ほど関係性が深くない人たち同士が日常的によく身体的な接触をする。
『人とはできるだけ物理的な距離をとりたい』と常々考えている自分みたいな人間は、涼子のバイト先では絶対に働けない。
従業員同士のスキンシップが多すぎる(昔かたぎのセクハラも)。
もしこの小説の舞台が東京ならば、言葉を標準語にしても、登場人物たちのセリフや行動は大きく変わるのではないだろうか。
もっとよそよそしく、オブラートでくるんだような物言いに?
それとも物語の中でも話題になっているように、大学まで進学したあとで社会に出て働く者と、高卒で社会に出てそのままずっと働き続けなければならない者とでは、セリフや行動パターンが変わってくるのか?
それは変わるだろうと思うし、関西と関東でもやはり人との距離の取り方が変わるとあらためて思う。
別にそれはこの本が伝えたい主題ではないだろうけど、久しぶりに実家に近い地方の人間の泥臭さに触れて、ちょっと身が縮んでしまった。
一方で、心の奥底では、誰もがもっと親密なスキンシップを求めているのだろうということが、涼子とオストメイト仲間とのやり取りから伺える。
お互いを肌で温め合うような動物的な触れ合いを…
誰もがありのままで受け入れられる関係を…
塩の道
『私の盲端』と一緒に収録されている『塩の道』は、アラフィフの医者が主人公だ。
医者というのは皆、無表情で何を考えているのか分からないのが常だ。
だから、この小説に医者の内面が書かれているのは面白い。
しかも絶対に口には出せない医者の本音とか、病院の裏側だ。
作者の朝比奈秋氏は医者だったそうなので、この主人公が作者自身だと錯覚されても文句は言えない。
この主人公の伸夫は普通なら主人公に抜擢されないタイプの医者だ。
30代から40代の半ばまでは関東の救急病院で忙しく働いていたが、その後福岡の病院に移った。
50歳手前の現在は、颯爽として頼もしいところがまったくなく、睡眠障害のせいでいつも疲れており、気力が尽きている。
とはいえ、やる気のある職員は、この青森の僻地の病院からすぐに逃げ出してしまうそうなので適材適所といったところだろうか。
漁村にある病院なので、村民のなまりは強い。
それがいい味を出している。
最初読んでいて『東北弁だけど秋田弁じゃない』と思った。
東京の前は秋田に9年間住んでいたからだ。
ほどなく舞台が青森だと分かって納得した。
でも『秋田も青森も変わらないなー』と、とてもおかしく思ったのが、村人(特に漁師)が重い病気にかかっても、ひどい怪我をしても、黙って「ギリギリまで我慢する」ところだ。
状態を聞いても、「まるで大したことではないように話す」。
これでは治るものも治らなくなってしまう。
私の夫が東北人(出会った頃は秋田に実家があった)でまさにこのタイプなのだ。
伸夫:「(無医村時代)漁師は病気になった時どうしてたんですか」
岡崎:「病気になったって、やづら黙って死んでいぐのよ。何の病気かわがらんまま、あいづらは耐えるんよ。漁師っでのは毎食干物やら塩辛やらでよ、昔っがら行く末は中風のヨイヨイになるのが決まってらで。そえでも半身であいづら沖に出るんよ」
(※岡崎は60歳くらいの看護婦)
(※中風は脳血管障害により体に麻痺、言語障害などの後遺症が残ること)
(※ヨイヨイは体の一部が麻痺などによって自由がきかなくなること)
『塩の道』は昔ながらの小説スタイルで、僻地の寒村の暮らしを切り取ってうまくスケッチしている。
朝比奈秋氏は方言を作品にいかすのがうまいようだから、日本各地を舞台に、その土地の特徴をスケッチして小説をもっと書いてほしい。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-
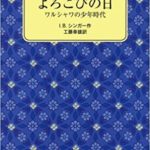
-
英国におけるユダヤ人差別 『オーウェル評論集』ジョージ・オーウェル著(岩波文庫) オーウェルは大変率直な人だ。「英国におけるユダヤ人差別」などという誰もが避けて通りたいテーマでも自分が見聞きしたユダヤ …
-

-
某スーパーで試食販売をしていた。 ちょっと離れた場所には別の試食販売員がいた。 互いの販売場所が近いので、しかもこのおばさんは明るくてとても性格がいい人だったので、ときどきおしゃべりして仲良くなった。 …
-
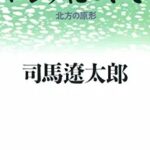
-
『ロシアについて』を読むと意外な点が多々あった。 まず「ロシア人によるロシア国は、きわめて若い歴史をもっている」と書かれている。 ロシア国家の決定的な成立は、わずか十五、六世紀にすぎないのです。若いぶ …
-
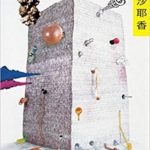
-
(※ネタバレありです) はじめに 芥川賞を受賞した時から気になっていた。 お仕事小説が好きだし、自分自身がコンビニで働いた経験があるので、他の人があの仕事をどのように感じているか知りたかった(なので佐 …
- PREV
- ジャングルへ行く!:医者も結婚もやめて/林 美恵子
- NEXT
- 名古屋駅西 喫茶ユトリロ/太田忠司