イギリスを知るためのおすすめ映画
投稿日:2019年1月29日 更新日:
(※ネタバレありです)
1.クイーン
1-1.あらすじ
2006年に公開されたイギリス(フランス/イタリア)映画(スティーヴン・フリアーズ監督)。
題名のとおりエリザベス女王が主人公だ。
ヘレン・ミレンが人間臭い女王を演じているので、女王に好感がもてる。
王室の人たち、女王とその家族たちがどのような日常生活を送っているのか、その一端をかいまみることができる。
この映画はダイアナ元皇太子妃の事故によって王室が巻き込まれた一連の騒動を中心に描いている。
王室にとってダイアナはすでに一民間人である。
だが、国民はロイヤルファミリーの一員としてダイアナを敬愛していた。
ダイアナの事故を王室が完全に無視することは、国民にとっては許せない事態だった。
王室に対する国民感情は急激に悪化し、ダイアナの葬儀直前に世論調査をしたところ、国民の4人に1人が王制の廃止を望むというショッキングな数値があらわれた。
この騒ぎの渦中、王室と国民の間をとりもったのがトニー・ブレア首相(マイケル・シーン)だった。
庶民派のブレアは国民感情を正確に読みとり、エリザベス女王にも態度をあらためるよう大胆にアドバイスする。
その結果、女王も首相に折れてダイアナに対する声明を発表した。
王室と国民の対立はこれによって緩和し、ブレア首相の人気は高まった。
1-2.感想
日本にも天皇が存在するので、そういった人たちの素顔をのぞきみるような面白さがあった。
また、エリザベス女王とその家族の本音を耳にして、王室の人たちもやっぱり私たちと同じような人間なんだと思った。
ヘレン・ミレン演じるエリザベス女王は一生懸命に自分の責務を果たそうとしている女性だ。個人的な感情をあらわにせず、常に威厳をたもつよう最大限の努力をはらっている。
いたましいような、いじらしいような部分があり、憎めないキャラクターに仕上げてある。
ユーモアのセンスがあるのも好印象だ。
首相就任時からエリザベス女王と交流し、この映画の第2の主人公となっているトニー・ブレア首相も愛すべき人物として描かれている。
その妻のシェリー・ブレア(ヘレン・マックロリー)はかなり過激な王制廃止論者だ。
エリザベス女王に対しても反発を隠さない態度は、面白いようなハラハラさせられるような気持ちにさせられる。
トニー・ブレアも首相就任前はシェリー同様の革命派だったらしいが、エリザベス女王と対話を重ねるうちに親近感をいだくようになり、女王を擁護する発言が増えて妻をイライラさせる。このへんの態度の変化、人情の機微も面白い。
イギリスと王室は切っても切れない関係にあるので、この映画はイギリスを知るのに役に立つ。
エリザベス女王のクイーンズ・イングリッシュも堪能できる。
次に紹介する『わたしは、ダニエル・ブレイク』の庶民が話すクセのある英語と聞き比べてみるとまた面白い。
2.わたしは、ダニエル・ブレイク
2-1.あらすじ
2016年に公開されたイギリス(フランス/ベルギー)映画(ケン・ローチ監督)。
59歳のダニエル・ブレイク(デイヴ・ジョーンズ)は大工だったが仕事中に心臓発作を起こし医者から就業をとめられた。
しかたなく国の支援手当を受給しながら暮らしていたが、更新の際に突然「受給資格なし」と認定されて支給を停止されることになった。
そのままでは生活がたちゆかなくなるので、再度受給できるように申請手続きをおこなうところから映画はスタートする。
またダニエルは、役場で20代のシングル・マザー、ケイティ・モーガン(ヘイリー・スクワイアーズ)と知り合い、その家族と交流を深めていく様子が全編をつうじてていねいに描かれている。
ダニエルは大工として真面目に働き、政府にきちんと税金をおさめてきた。
しかし政府は、病気になったダニエルを助けてくれない。
国の支援制度は存在するのだが、効率的に運営されておらず、問い合わせの電話1本かけるだけでも1時間近く待たされるしまつだ(電話料金も負担しなければならない)。
何度足をはこんでもムダに部署をたらい回しにされるような非人間的な扱いしか受けないので、ダニエルはストレスのかたまりになり、絶望して、抗議行動を起こして警察に逮捕される。
一方、ケイティは18歳のときに「特別」だと思った男性と出会って長女を生み、それから別の男性と出会って長男を生み、現在はひとりで子育てをしている。もともとロンドンに住んでいたのだが大家とトラブルを起こしてアパートを追いだされ、その後2年間は生活保護で暮らしていた。それから政府に紹介されてニューカッスルの現在のアパートに移り住んだ。ニューカッスルはロンドンよりもさらに北に位置するので冬は厳しそうだ。見知らぬ土地でケイティにはたよれる人がひとりもいない。毎日子供を学校に送り迎えしなければならないので求職活動は難航している。フードバンクで食料をもらって家族3人はギリギリ生きているけれども、いずれ破たんしそうだ。
ダニエルは善人なので力いっぱいケイティをサポートしようとするが、生活に困窮した者同士がいくら気づかい合ってもできることは限られている。ともに日々の生活にくたびれて果てて、体力と気力を消耗し、相手が落ちぶれて力尽きるのを見届けることしかできない。
そのように貧困層が救われないイギリスの現状を描いたのがこの映画だ。
2-2.感想
新潮社の『波」という月刊誌にはブレイディみかこの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」というエッセイが連載されている(1冊税込100円)。
彼女はイギリスの南東部ブライトンでアイルランド人の夫と中学生の息子と暮らしている。この親子はとても仲がよい。息子の学生生活を中心に、日常生活でであう格差・人種差別・貧困をめぐるトラブルや深刻な問題などを率直にレポートしたものだ。
とても興味深く、面白く、毎号まっさきに読んでいるお気に入りの連載だ。
この中でも政府の緊縮財政が貧困層を直撃していて、人々は生活苦にあえいでいるということが報告されている。国がたよりにならないので住民同士で助け合っているが、それにはやはり限界がある。
EU離脱も含めイギリスの現状をみていると、日本はいまのところまだマシだという気分になってしまう。でもいずれイギリス同様に貧困がどんどん広がっていくのだろうとも思い、怖くなる。
この映画ではケイティのロンドンなまりの英語と、移転先の住民のニューカッスルなまりの英語がメインで話されている。
どちらもクイーンズ・イングリッシュとはだいぶ響きがちがう。
ニューカッスルはなまりが強く、他のイギリス人が理解できないほどだという。
英語に興味がある人は言葉を聞いているだけでもこの映画を楽しめると思う。
2-3.寝室税(Bedroom Tax)
この映画には「寝室税」という聞きなれない単語が登場する。
寝室税は、上流階級出身のキャメロン政権の緊縮財政政策の一環として2012年の福祉改革法(Welfare Reform Act 2012)に導入されたそうだ(2013年4月1日から就労年齢者全員に適用)。
政府から住宅手当を受けている公営住宅などの住民が必要以上に余分な部屋(寝室)を所有しないように罰則をさだめたものだ。
■1寝室に対する割り当ては・・・
・大人のカップル
・16歳以上の他の各人
・16歳未満の同性の子供2人
・性別に関係なく10歳未満の子供2人
・その他の子供(主な家庭が他の場所にある里子以外)
・一晩の介護を必要とする人のための非居住介護者(または介護グループ)
・寝室を共有できない身体障害のある子供が必要とする部屋
■罰則は・・・
・許容量に対して予備の寝室が1部屋あれば住宅手当は14%削減され、2部屋あれば25%削減される。
(※WikipediaのUnder-occupancy penaltyの記事をGoogle翻訳して参照)
3.スリーピング・ディクショナリー
(※ネタバレありです)
3ー1.あらすじ
大英帝国の植民地サラワク(マレーシア)を舞台にしたロマンス映画。
物語は1930年代に始まるので、そんなに昔の出来事ではない。
恋に落ちるカップルは、イギリス本国から植民地の管理のために派遣された若い行政官であるジョン・トラスコットと現地の美しい娘セリマ(行政官の夜の妻役兼語学教師役を務める「スリーピング・ディクショナリー」)。
しかし、2人が本氣で愛し合い、結婚を望むのは2人の立場上、過去の慣習上、絶対に許されないことだった。
古い慣習が人を縛り、当事者も、周りの人をも、不幸にする。それが描かれている。
幸い(?)この映画では、ジョンが、結婚して、妊娠したイギリス人の妻セシルを捨てて、セリマと再会し、密かに出産された自分の息子と3人で植民地で生きることを決めるラストで終わっている。
本妻のセシルも、夫が現地妻セリマのことをずっと思い続けていることに気づき、自分も妊娠しているにもかかわらず、夫をセリマの元に行かせる。
セシルの父親もサラワクの行政官だった(現在も同地で監督官を務めている)。父親と現地のスリーピング・ディクショナリーの間には娘が1人いた(父親は娘には名乗らず密かに成長を見守っていた)。その娘がセリマだった。
セシルの母親も公認の現地妻の存在に苦しめられてきた。「現地の慣習だから」と、割り切って考えようと努力するが、嫉妬心は抑えようもない。
そんな母親の姿を見てきたセシルだからこそ、同じような生きかたはしたくないと思い切った決断ができたのだ。
3ー2.感想
イギリス人は、特に上流になればなるほど、社会の慣習に従い、自制心を発揮すること求められている。この映画の登場人物たちのように、自己を押しころす生きかたはとても苦しそうだ。
妻としての義務を果たすことを最優先して、我慢に我慢を重ねて生きてきたセシルの母親は、古風なイギリス人女性の典型に見える。基本的には感情を抑えて人に接するが、冷静な口調でチクリと皮肉を言うクセがある。
たまりにたまったストレス+自制心が皮肉屋のイギリス人を生みだしたのかもしれない。
4.ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス
マイ・英国ブームの一環で見にいった。
ヴィヴィアン・ウエストウッドというファッションブランドは名前しか知らなかった。
ヴィヴィアン・ウエストウッドという人は圧倒的な存在感をもつ人物だ。
現在77歳。
子供の頃からファッションデザイナー兼クリエイターの才能があった。
そして反権力・永遠の反逆者。
その2つの要素が結びついたものがヴィヴィアン・ウエストウッドというイギリスのファッションブランドだ。
ファッションに反権力を持ち込むなんてありえる?と思うが、そこがヴィヴィアンのオンリーワンな個性なのだ。
自己表現としてファッションを利用する。
「これが私だ」という一環した姿勢を崩さない。
他人からどう思われるかなんて気にしない。ノー・ルール。何でもアリ。ノー・タブー。「私は私」というのがヴィヴィアン・ウエストウッド・スタイルだ。
その姿勢はすごくカッコいい。若い頃からそうだったし、驚くべきことに、77歳になっても全然変わらない。
最近、自分が年をとることに漠然とした不安を抱いていた。
でもたまたまこの映画を見て、頭の中のモヤモヤが消えていった。
年をとることが怖くなったら、ヴィヴィアン・ウエストウッドを見ならうといい。
あんなにオシャレでカッコいいおばあさんはどこにもいない。あんなふうに年をとりたい。
5.ハワーズ・エンド
1992年公開。E・M・フォースター原作。ジェームズ・アイヴォリー監督。エマ・トンプソン、アンソニー・ホプキンス、ヘレナ・ボナム・カーター出演。
(※ネタバレありです)
今から約100年前のイギリスが舞台になっている。
イギリスの映画を見ると、上流階級になればなるほど登場人物の大半が働かずに毎日ブラブラと遊んで生活しているようで、とても不思議な気持ちになる。
『ハワーズ・エンド』の主人公姉妹も、何者なのかよくわからない。あまり働かずに豊かな暮らしをしているように見える。姉のマーガレット(エマ・トンプソン)は気立てのやさしい女性で、争いごとを好まない穏やかな性格だ。人の世話をするのが好きで、近所に引っ越してきた老婦人ルースの世話を純粋な善意から焼くことで、結果的には「ハワーズ・エンド」という郊外にある邸宅を手に入れることになる。
一方、妹のヘレン(ヘレナ・ボナム・カーター)は、気立てが荒く、情熱的で激しい性格。当たり前とされている社会のルールにも、間違っていると思えば場所を考えずまっこうからケンカを売る、家族の中のトラブルメーカーだ。だが、貧しい人、弱者には思いやりがある。富める者、成功者には厳しい。文学好きなインテリで理想主義者なのだ。
姉妹に弟を加えたジュレーゲルの3人家族と、向かいに引っ越してきた、前述のルースを含むウィルコックス家の交流がこの映画の主題で、タイプの異なる2家族が対立したり、ケンカしたり、婚姻関係を結んだり、妥協/和解したりしながら、最後はおさまるべきかたちにおさまっていく様子を描いている。
2家族だけでも混乱するのに、さらにここに階級がちがう1家族がからんでくる。シュレーゲル家やウィルコックス家から見れば格下の、貧しくがらの悪いレナード&ジャッキー・バスト夫妻だ。
まずヘレンがレナードと偶然知り合い、レナードの不遇に同情しておせっかいをやく。レナード→ヘレン→マーガレット→ヘンリー・ウィルコックス(アンソニー・ホプキンス)とつながり、さらにヘンリーが昔ジャッキーの愛人だったことも判明する(!?)
また情熱的家のヘレンはヘレンで同情が高じてレナードと関係をもってしまう(!?)
こうして書いていると本当にはちゃめちゃで泥沼の3家族みたいだが、映画はあくまでも上品で、ハワーズ・エンドまわりの風景などが大変美しい。
つまりこれがイギリス人の生き方なのだと思う。表面的にはあくまで上品で美しく、基本的には階級ごとのあるべきルールに従い、極力争いごとは避けて、可能なかぎり穏便におさめ、話し合いと妥協で問題を乗り越えていく。
大多数の人は「穏便に、穏便に」と願っているが、現実にはそうは問屋がおろさない。ということで、異端児ヘレンが台風の目となり周りを巻きこんでひっかき回す。
イギリス映画でイギリス女性をたくさん見るが、ヘレナ・ボナム・カーターは他のイギリス女性とは顔つきや雰囲気がだいぶちがう。母方の祖父がスペイン生まれだから髪の毛や瞳が黒っぽいのだろうか? かなりの名家のお嬢さんだ。女優になってしまったところを見ると、実生活でも跳ねっ返りの異端児なのだろうか? とにかくこの映画のヘレンにはぴったりはまっていて、キャラが立ちまくっている。
姉のマーガレットは、シュレーゲル家で暮らしているときは家族でおしゃべりしまくってにぎやかに自由を謳歌していたのに、ヘンリーの求婚を受けてウィルコックス家に入ってからは、口数が少なくなり、つねに夫を立てて、波風は立てず、身をつつしんで生きるようになった。
他のイギリス映画の女性も、上流階級になればなるほど「忍」の一字で生きているように見える。日本人の女性の生き方にもすこし似ている気がする。しかしこれは100年前が舞台の映画だから今はまったくちがうと思いたい。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-

-
アメリカと距離をおくために 日本にとってアメリカは親のような存在に思えることがある。生まれたときからそばにいて、考え方、物の見方、センスなどにかんして絶え間なく影響を及ぼしてくる。だからアメリカ人が書 …
-

-
(※ネタバレありです) イギリス・シェトランド諸島を舞台にしたアン・クリーヴスの人気シリーズの7作目。 主人公のジミー・ペレス警部は、亡くなった婚約者フラン・ハンターの娘であるキャシーと一緒に暮らして …
-
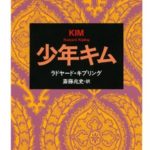
-
キプリングとインド 大英帝国時代(インド統治期間は1858-1947)、植民地のインドなどに赴任し、その地で子供を産み、育てるイギリス人は多かった。『少年キム』の作者であるラドヤード・キプリングは、イ …

