ぶどうの木/坂本洋子
投稿日:2020年11月25日 更新日:
2020年6月27日付朝日新聞朝刊”be”の「フロントランナー」で坂本洋子さんのことを知った。
里親として他人の子どもを18人も育ててきたという。
「こんな人がいるんだ!」と驚き、感動した。
実の子どもを1人育てるだけでも想像以上に大変だということが最近はよくいわれている。
なのに里親となり、重い事情のある子ども(障害児含む)を次々と養育していくなんて、神ワザとしか思えない(坂本さん夫婦はキリスト教徒だ)。
もっと詳しい内容を知りたいと思い、図書館で坂本洋子さんが書いた『ぶどうの木ー10人の”わが子”とすごした、里親18年の記録』(単行本は2003年出版)を借りて読んだ。
この本は里親の実体験を書き記した内容だが、これを読んで「私も里親になりたい!」と思う人がいるだろうか・・・と思うほど、厳しい現実が描かれている。
子ども自身にはまったく非がないのに、特に乳幼児(2~3歳)時代に安心感を得られない環境に置かれていた子どもは、その後の人生でも不安定な行動を取りがちになる。
また施設で集団で育てられるという経験によって、家庭で育てられるのとは異なる行動パターンが生まれることもある(所有意識が希薄/自分の物と他人の物の区別ができない等)。
そして小学校に上がり、他の一般家庭で育った子どもたちと生活するようになると、施設で育った子どもの行動だけが集団生活から浮き上がってしまう。
他の子どもとトラブルを起こして学校から電話がかかってくることなど日常茶飯事だった最初の里子の純平君。
里親になることは「多様性」と真正面から向き合うことのようだ。
里子がたとえ3歳であってもすでに生まれてから3年分の経験をずっしりと背負っており、とても一筋縄では行かない。
こういう現実があるということを知りたい人に読んでほしい。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-
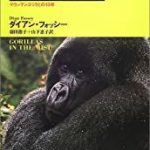
-
1. 『霧のなかのゴリラ』(ダイアン・フォッシー著) 1967年に始まり10年以上続けられたダイアン・フォッシー博士のルワンダにおけるマウンテンゴリラの観察記録である。 ゴリラと人間のDNAの違いはわ …
-

-
(※ネタバレありです) 1. 念入りに殺された男/エルザ・マルポ 著者のエルザ・マルポはは1975年フランスのアンスニ生まれ、ナント育ち。 小説の舞台は前半はフランス北西部のナントの村、後半はパリ。 …
-

-
(※ネタバレありです) スウェーデンの作家ヘニング・マンケルが書いた『殺人者の顔』を読んだ。 大人気のクルト・ヴァランダーシリーズ第1作目だ。 想像を超える面白さで、衝撃を受けた。 舞台はスコーネとい …
-

-
(※ネタバレありです) 英題:Norwegian by Night (2012) 舞台はノルウェーで、主人公はシェルドン・ホロヴィッツという名の82歳のユダヤ系アメリカ人。 この設定もさることながら、 …
-
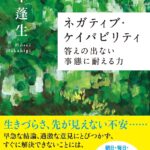
-
ネガティブ・ケイパビリティ-答えの出ない事態に耐える力/帚木蓬生
ネガティブ・ケイパビリティ 生きているといろんな問題が発生する。 自分に関するトラブルなら自分でなんとか事態に対処できるからいい。 しかし実際に起きるトラブルのほとんどが自分以外の他人に関わるものだ。 …
- PREV
- 高卒の国家公務員の給料を調べてみた
- NEXT
- 池波正太郎の銀座日記[全]