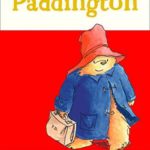人類堆肥化計画/東千茅
投稿日:2021年3月23日 更新日:
(※ネタバレありです)
書評を読んで『人類堆肥化計画』という刺激的なタイトルに興味を抱いた。
すごく面白いか、すごく面倒臭くて変な内容かも。
買うか買わないかで、かなり悩んだ。
インターネットで『人類堆肥化計画』を読んだ感想をチェックしたけど、数が少なくあまり参考にならなかった。
東千茅という著者の名前で検索すると対談記事が見つかって、写真もあり、思ったよりも若い人だとわかったので(1991年生まれ)、『内容が変でもそこまで変じゃないだろう』と思った(このタイトルで著者50代以上だと文章が硬すぎたり、センスが現代離れしている可能性があり危険なので買わなかったと思う)。
対談記事:https://book.asahi.com/jinbun/article/13999827
対談中に、著者は「存在してしまっていたことに納得がいかない」「自分を生み出した世界に落とし前をつけさせる」・・・自分の存在に大きな違和感を持っているとあった。
私もよく『勝手に存在させられて迷惑』と感じるので共感を抱き、この存在に対する違和感を脱却するヒントがなにか見つかるかもと期待してアマゾンで本を注文した。
本が届いて「はじめに」を読むと、著者の「生い立ちや里山に移り住んだ経緯」が第三章に書いてあるとわかったので、まずそのことを最初に知りたいので第三章から読むことにした。
変則的に第三章から読んだのは正解だった。自分の生い立ちを語る文章は難解になりにくいからだ。
最初に著者のことをざっと理解し、ちょっと親しみを持てたのもよかった。
第三章、第四章を読んで、里山での春夏秋冬をスケッチする挿話を読み、第一章、第二章を読んで読了した。
第一章はこんな感じだ。
わたしが里山生活に向かったのは、より愉しい日々を求めてのことだった。都会での生活はわたしにとって、生きることの迫真性に欠ける不十分なものだった。溢れているのは人間ばかりなうえ、なにもかもが間接的で、その分だけ悦びも希釈された。わたしが渇望したのは〈生きることを生きること〉であり、自分の生を完膚なきまでに味わい尽くすことである。
確かに、自分の存在に大きな違和感があるとき、里山に向かい自給自足の生活を始めるのは根源的な生を生き直す第一歩として有効だと思う。
大地とつながり、土をいじり、命を生み出し育む過程に直接参加する。
他の人間とかみあわない人は、人間の代わりに、里山で無数の生き物と交流を深めることができる。人間よりも虫、動物、植物などの生物が好きな人に里山生活はおすすめだ。
私は人間嫌いだが、虫もそんなに好きじゃないのでこの本を読んでも里山生活をしたいとは思わなかった。
ただ都会で表面的に生きるだけじゃなく、田舎で〈生きることを生きる〉選択肢もこの世に存在するということが再確認できた。
タイトルになっている『人類堆肥化計画』というのはこの本の中でどちらかといえば比喩的に使われている。
まるでミステリ小説のごとく、人間を土に埋めて堆肥にするために殺す計画が書かれているわけではない。
「人類堆肥化」=「わたしは生命を奪いつつも、堆肥よろしく生命を育んでもいる」という意味。または・・・
自分一人が生きるためだけなら、里山や後進の生育にまで手を出さなくていい。だが、わたしは、外臓で作物や家畜たちと癒着するばかりか、その過程で里山という怪物の胃袋で分解されて堆肥になっていた。堆肥になったわたしは、自分一人の生育だけでは飽き足らず、さまざまな者たちが生きうるそこそこ広い土壌を育みはじめる。
・・・というような表現。
『人類堆肥化計画』についてもっとわかりやすい説明は「おわりに」に書いてある。
言葉としてはアニメのエヴァンゲリオンに出てきた「人類補完計画」を連想的にもじったものという。
有機物が壊されて堆肥が作られるのと同様に、人-間も壊すことで堆肥にすることができるはずだと考えたのである。人間を堆肥化して大地の栄養にしたほうが、よっぽど「補完」だとはいえないだろうか。人類に欠けているものは、異種たちと地上で共に生きる欲望なのだ。
『人類堆肥化計画』は、自分を取り巻く世界との折り合いが悪い人におすすめ。生き抜くヒントが見つかるかも。
[東千茅/略歴]
1991年大阪生まれ。保育園では問題児。小3~5年は台湾でのびのびと過ごす。中学時代~高1、同調圧力に苦しみ精神状態悪化。高2でカナダに留学。鬱化し帰国。大1~3は弓道部で活躍。部活をやめると再び空っぽに。何をしても意味や価値や希望を見出せない。大学5年で中退。畠に向かって今に至る。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-

-
図書館で『マイ・ストーリー』を予約した オバマ元大統領の妻であるミシェル・オバマについては顔と弁護士だったということしか知らなかった。 ある日、本屋で『マイ・ストーリー』の試し読み版を読むと、とても面 …
-
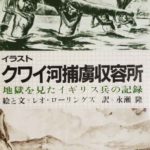
-
クワイ河捕虜収容所 (地獄を見たイギリス兵の記録) レオ・ローリングズ(著・イラストも) AND THE DAWN CAME UP LIKE THUNDER by Leo Rawlings 出版日 1 …
-
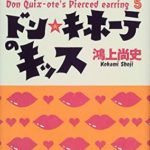
-
鴻上尚史さんの著作を読むのは初めてで、『ドン・キホーテのキッス5』はとても面白かった。 なぜシリーズの5巻から読み始めたかというと、図書館に『ドン・キホーテ』シリーズの5・7・8巻しかなかったからだ。 …
-

-
夫の若年性認知症をうたがう 同学年の夫は現在53歳だ(私は早生まれで52歳)。 もともと記憶力が良い人なのに、最近とても忘れっぽくなった。 『老化のせい?』と考えると、『まぁ、しかたない』と思えるが、 …
- PREV
- 高峰秀子 夫婦の流儀
- NEXT
- 心療内科を初受診した(安かった)