身体感覚を取り戻す/斎藤孝
投稿日:2020年11月20日 更新日:
日本人の身体は存在感を失った?
日本人の身体が特にここ50年で(2000年時点)悪い方向に大きく変わってきたことが説明されている。
確かに現代の日本人の身体は、着せ替え用のマネキン程度の存在感しか示すことができていない。
現代人は毎日せかせかと脳を働かせることにほとんどすべての意識を集中して生きている。
身体の働きについては最低限の注意しか払っていない。
不調になるまで放置しがちだ。
子ども時代から身体はつくられる
土門拳が1953年に撮った写真が本書に収録されている。
子どもが夢中で「馬乗り遊び」をしている写真だ。
昔の日本の子どもはそのへんの路地で男女入り乱れて身体を使って激しく遊んでいたことがその写真から見てとれる。
馬乗り遊びをすれば、本気で踏ん張るので自然に足腰が鍛えられ、身体が丈夫になる。
今や路地で身体をフル活用した馬乗り遊びをしている子どもなど見る機会はない。
馬乗り遊びは、1960年生まれの著者が小学生の頃は流行っていた遊びらしいが、著者より十数年後に生まれた私の時代にはやっている子どもはいなかった。私自身もそういう遊びは知らない。
身体の直接的な触れ合いはコミュニケーションの基本だと斎藤氏は言う。
そうかもしれない。
でも現代の日本では他人の身体に触れることはほとんどなくなっている。
自著の中で『身体感覚を取り戻す』を紹介していた演出家の鴻上尚史氏も、日本人は性的接触以外ではめったに互いの身体に触れ合わないことを指摘していた。
確かにそうだ。
私自身も他人の身体の温かみとかが苦手な潔癖症タイプである。
本来の動物的な感性からすれば、体温の温かみは安心感の本源に違いないが、なぜか日本人の感性は逆方向に進化してきた。
安心感は求めているのに人と触れ合うのが苦手というのは、どういう精神/身体構造になっているのか?
それこそまさに著者が『身体感覚を取り戻すー腰・ハラ文化の再生』の中で非常に心配しているテーマなのだ。
消えた「腰・ハラ文化」
江戸時代はもとより戦後から1960年代くらいまでは日本人の間で「腰・ハラ文化」が親から子に脈々と継承されていたという。
「腰・ハラ文化」というのは、たとえば相撲を取るときや祭りでみこしをかつぐときに腰やハラにぐっと力を入れるしぐさ、身体の重心を腰・ハラのあたりにおき、肩の力は抜いている。
そういう状態の方がいざというときは瞬時に力を発揮しやすいそうだ。
長らく腰・ハラを中心にした身体の使い方が日本人の伝統的な身体文化だった。
私は1970年代の生まれで、腰・ハラ文化が絶滅する前の最後の世代かもしれない。
中学生になるまでテレビゲームがなかったので、それまでは昭和の子どもらしく学校の休憩時間中(先生の先導で授業中も)や放課後、外で暗くなるまで身体を使って走りまわって遊んでいた(相撲、鬼ごっこ、缶蹴り、馬跳び、ゴムとび、ドッヂボール、野球、かくれんぼ、だるまさんが転んだ、ケンケン、メンコなど)。
だから著者が言わんとすることはよくわかる。
でもやはりテレビゲームのインパクトは強烈で、インベーダーゲームとか、ブロックくずしを近所の家の子が持ってると、何よりもそれをいちばんやりたかった。
やりはじめると、ずっとやり続けたくなった。
テレビゲームだけが原因ではない。
明治以降の近代化/欧米化と、敗戦により日本独自の文化に対して日本人が自信を失ったこと、公共交通が発達してみんな昔のように長距離歩かなくなったことなど、時代に流されて日本人の腰・ハラ文化はすたれていった。
腰・ハラ文化がすたれると、腰・ハラなどの身体の部位を使った慣用句も日常生活から消えていった(「腰を入れる」「へっぴり腰」「および腰」「腹にすえかねる」「腹におさめる」など)。
子どもがぐずったらおんぶしてやるといい
昔の日本人がよく行っていたことに「背負う」ということがあった。
子どもも親の手伝いで重い荷物をしょって長距離を歩いたし、幼い兄弟をおんぶして世話をしなが日常生活を送っていた子どももいる。
背負うときには腰・ハラ・足にぐっと力を入れる必要がある。
かつては毎日重い荷を背負うことで日本人の身体は鍛えられていった。
背負うといえば、最近の親はあまり子どもを背負わなくなったかもしれない。
斎藤氏によれば「背負われるときの安心感には格別のものがある」
ぐずっている子どもをおんぶしてしばらく呼吸を合わせていると、しばらくすると子どものほうから降りていく。
ぐずったり、へたりこんだりしているときには、言葉よりも背負うほうが効く。
これは現代にも通じる身体感覚だと思うので、ぐずりがち、へたりがちな子どもがいれば、一度おんぶを試してみるといいかもしれない。
でも腰・ハラ文化がすたれた今、親側の腰がおんぶの姿勢・子どもの重みに耐えられるかどうか・・・
「腰・ハラ文化」とともに著者が重視しているのが「息の文化」で、呼吸法や息づかいについても考察されている。
呼吸は私たちの身体で毎日24時間行われているものなので、身体に良い方法でやったほうがいいに決まっている。
斎藤氏は好奇心が強く多芸というか、呼吸法でも何でも気になったものは専門家について自分の身体で試してしまう。
『身体感覚を取り戻す』には、著者が現代人に意識して日常生活に取り入れてほしいと願う、身体を元気にするためのヒントがぎっしりつまっている。
身体のことに興味がある人はぜひ読んでみてほしい。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-
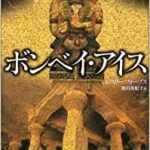
-
(※ネタバレありです) ヒジュラと主人公 ヒジュラ(男でも女でもない性別者)が登場するインドを舞台にした小説ということで興味をひかれて読んでみた。 Wikipedia【ヒジュラー】のウェブページ(写真 …
-

-
ダイエットが失敗でも 10日後に健康診断があるので、すこしでも体をしぼろうと思った。 ダイエットの方法としては、 (1)間食しない/甘いものを食べない (2)夕飯のカロリーを抑える(和食中心) (3) …
-

-
久しぶりの外飲み 6/15(月)-6/21(日)の週は、東京のコロナ感染者数が1日平均30人台だった(*東京都の発表データ参照)。 「コロナはもう終わりかも」と思い、3か月以を上自粛していた外食を久し …
-
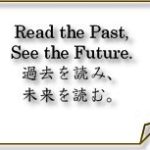
-
まえがき 池波正太郎の『むかしの味』の中に、以下の記述がある。 当時、木下仙という作家の、モダンな山岳小説……というよりは、上高地のキャンプ小説が好きだったので、上高地では四度びほどキャンプをした 引 …
- PREV
- ケバブサンドを作ってみた
- NEXT
- 鮭の白子フライ
