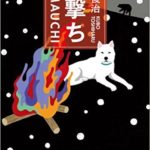お能健康法/井上和幸
投稿日:2021年1月6日 更新日:
『お能健康法』の副題は「すり足と呼吸で身体がよみがえる!」。
能なんて興味がなくて(醸す気配がちょっと怖い)、普段なら図書館でも絶対に手に取らない本だ。
実は『お能健康法』は図書館の福袋に入っていた。
1月5日の正月明けの開館日に近所の図書館に行った。
昨年もこの時期にあったが、何が入っているかわからないあの紅白の紙製の福袋が折りたたみテーブルに並んでいた。
ワクワクしながら1つ選んで貸出しカウンターに持って行った。
私が選んだ福袋の中身の1冊が『お能健康法』だったのだ(全3冊入っている)。
正直、最初見たときはギョッとして引いたが、本が好きなので手元にあれば読まないはずがない。
結局、読んで良かった。未知の世界の扉が開いた感じ。
能の発祥は600年前の室町時代までさかのぼるそうだ。
有名なのは観阿弥・世阿弥親子。
そこから現在まで能は脈々と続いている。
続いているということは、一般人にはわかりにくくても、存在理由があるということだろう。
タイトルの『お能健康法』については、とにかく能は鑑賞するだけでも身体に良く、その音楽(謡)を耳で聴くだけでも心身が健康になるという。
もちろん自分でうたい、ステップ(すり足)を真似るともっと良い。
本の中にも能によって病気が治ったなどの奇跡的な実例が記述されているが、論は証拠で試しに本書イチオシの音楽(謡)を聴いてみようと思う。「西王母」という曲だ。
能のすり足も一度試してみようと思う。
心身ともに健康になれるなら何よりではないか。
ただ、そんなに能が身体に良いなら健康法としてもっと流行っても良さそうだ。
みんな能について知らないということと、雰囲気がとっつきにくいことと、やはり若者の西洋化したセンスには合致しないのかもしれない。
執筆者:椎名のらねこ
関連記事
-
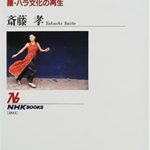
-
日本人の身体は存在感を失った? 日本人の身体が特にここ50年で(2000年時点)悪い方向に大きく変わってきたことが説明されている。 確かに現代の日本人の身体は、着せ替え用のマネキン程度の存在感しか示す …
-

-
ファイザー製ワクチン1回目 ファイザー製のワクチン1回目を打った。 初めての病院なので、徒歩15分のところを念のため1時間前に家を出た。 『早めに行けば、早めにワクチンを打って帰れるかも』という期待も …
-
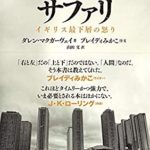
-
『ポバティー・サファリ イギリス最下層の怒り』(ダレン・マクガーヴェイ著) (※ネタバレありです) 労働者階級が書いた本を読みたい イギリス研究がマイブームなので、関連本を読んだり、映画を見たりしてい …
-
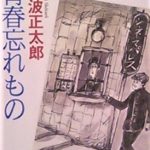
-
『青春忘れもの』by池波正太郎 池波正太郎への偏見 「鬼平=鬼の平蔵」こと長谷川平蔵は、池波正太郎の大人気シリーズ『鬼平犯科帳』の主人公だ。 当時江戸の町を跋扈した悪質な盗賊を逮捕するのが仕事で、今風 …
- PREV
- コロナ中の花粉症対策
- NEXT
- 夜の来訪者